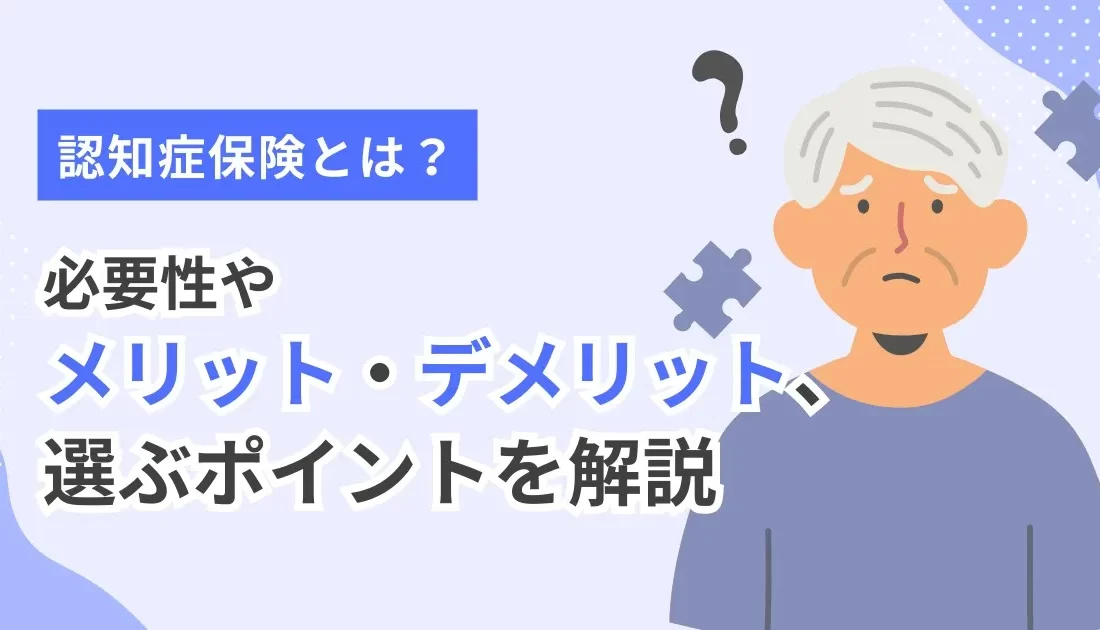最低限入っておくべき生命保険は?独身・既婚・年代別に必要な保険を解説

「不測の事態から家族や自分の生活を守るために最低限入っておくべき保険は何だろう?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。多くの種類の中から、自分に適した保険を選ぶためには、保険について基本的な知識を身につけることが大切です。
本記事では、代表的な保険の概要をはじめ、目的やライフステージ・年齢、性別ごとに最低限入っておくべき保険を詳しく解説します。
最低限入っておくべき生命保険の種類

生命保険にはさまざまな種類があるため、自分に適した保険を選ぶために、まずは全体像を把握することが先決です。そこでここでは、目的別に適した保険とその概要を表にまとめました。
|
目的 |
種類 |
概要 |
|
遺族に生活費を残す |
終身保険 |
|
|
定期保険 |
|
|
|
病気やケガに備える |
医療保険 |
|
|
がん保険 |
|
|
|
働けなくなった場合に備える |
就業不能保険 |
|
|
老後に備える |
個人年金保険 |
|
|
子どもの学費を貯める |
学資保険 |
|
代表的な生命保険のひとつは、死亡保障の終身保険や定期保険です。これらの保険に加入していると、自分が亡くなったあとも遺族の生活を支えることができます。
医療保険やがん保険は、病気やケガでの入院や治療の際に、公的医療保険では足りない分を賄うのに役立ちます。
また、就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときの収入減に備えたい方におすすめです。
老後に備えたい場合は、個人年金保険を検討しましょう。特に、国民年金にしか加入していない場合は、受け取る年金が少なく生活費が足りないといったケースが少なくありません。このようなケースでは、個人年金保険に加入することで、将来受け取る年金を手厚くすることが可能です。
ほかにも、子どもの学費を計画的に貯めたい場合は、学資保険を選択するとよいでしょう。毎月決まった保険料を積み立てることで、契約時に決めたタイミングで祝い金や満期保険金を受け取れます。
さらに、学資保険には保障機能があり、契約者である親に万が一のことが起こった際には、以降の保険料は免除されるのが大きなメリットです。もちろん、祝い金や満期保険金は予定通りに受け取れます。
「保険の種類が多く、自分にあった保険がわからない」とお悩みの方は、auフィナンシャルパートナーの「auマネープラン相談」をご活用ください。保険のプロがお一人お一人の状況や希望を踏まえて、提案させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
【遺族に生活費を残したい】最低限入っておくべき保険

家計の担い手が突然亡くなった場合、残された家族の生活は一瞬で不安定になります。特に、未成年の子どもがいる世帯や貯蓄が限られている場合は、生活費や教育費、住居費といった継続的な支出をどのように賄うかが大きな課題です。
公的な遺族年金はありますが、支給額は世帯の状況によって決まっており、必ずしも十分とはいえません。その不足分を補い、遺族が生活を維持できるように支えるのが生命保険の役割です。ここでは、生命保険の2本柱である終身保険と定期保険について解説します。
終身保険
遺族に生活費を残したい場合、終身保険に入っていると大きな安心につながります。終身保険とは、被保険者が亡くなったり、保険会社規定の高度障害状態になったりした場合に備えられる保険のことで、一生涯にわたって保障が続きます。
貯蓄性がある点も特徴で、途中で解約した場合は解約返戻金を受け取れるため、老後資金や急な支出への備えとして利用できます。ただし、早期に解約すると、解約返戻金は払込保険料の総額を大きく下回ることもあるため注意が必要です。
保険料の払込方法は、次の3つです。
- 終身払
- 有期払
- 一時払
終身払は、一生涯にわたり保険料を支払い続ける方法です。毎回の保険料を低く抑えられるため、若いうちは家計に負担をかけずに保障を確保できます。しかし、高齢になっても支払いが続くため、定年後の負担については考慮すべきでしょう。
有期払は、あらかじめ決められた一定期間で保険料を払い終える方法です。定年を迎えるまでに支払いを完了できるのがメリットです。
一時払は、契約時に保険料を一括で支払う方法で、まとまった資金がある方や相続対策として活用したい方に向いています。
定期保険
遺族に生活費を残しておきたい場合に、もうひとつの選択となるのが定期保険です。
定期保険も、被保険者が死亡した場合や高度障害状態に陥った場合に備えられますが、保険金が支払われるのは保険期間中のみという点が特徴です。一生涯保障が続く終身保険とは異なり、期間満了後は保障も終了する点には留意しなければなりません。
定期保険は保険料が低く設定されているため、子どもが独立するまでの間や住宅ローン返済中など、一定の期間に大きな保障を確保したい方におすすめです。
定期保険の保険期間には、年満了と歳満了の2つがあります。年満了は「加入から10年」のように、年数で設定する方法です。一方、歳満了は「65歳まで」のように、年齢をもとに設定します。
年満了では、満期後も更新が可能ですが、更新時の年齢に応じて保険料が見直されます。通常、更新時には、保険料が高くなるため注意が必要です。歳満了では、設定した年齢に達すると保障が終了し、一般的に更新はできません。
定期保険か終身保険かどちらが合っているか気になる方は、auフィナンシャルパートナーの「auマネープラン相談」までご相談ください。プロに無料で保険についての相談が可能です。保険選びの第一歩として「auマネープラン相談」をご活用ください。
【病気やケガに備えたい】最低限入っておくべき保険

生活習慣病やがんといった長期的な治療を要する病気や、突発的な事故やケガに備えられるのが医療保険やがん保険です。公的医療保険や高額療養費制度もありますが、公的保障の対象外となる費用が少なくないため、民間の保障を備えておくと安心です。
ここでは、病気やケガに備えたい場合に最低限入っておくべき保険について深掘りします。
医療保険
病気やケガに備えたい場合に最低限入っておくべき保険のひとつは、医療保険です。医療保険とは、入院や手術といった医療行為に対して給付金が受け取れる保険のことです。
医療行為を受けると、公的医療保険や高額療養費制度を利用しても、一定の自己負担分が発生します。さらに、差額ベッド代や先進医療の技術料などは公的保障の対象外です。医療保険に加入しておくことで、長期入院や高額な治療に伴う家計への負担を軽減できます。
医療保険の給付金の受け取り方法には、日額タイプと一時金タイプの2種類があります。日額タイプは、契約時に決めた金額が入院1日につき支払われるタイプです。入院日数が長くなるほど受け取れる金額が増えるため、長期入院への備えに向いています。
一方、一時金タイプは、入院や手術の際にあらかじめ決められた金額が一括で支払われるタイプです。交通費や生活費など治療以外の費用にも使えるため、使い勝手のよさが特徴です。
がん保険
病気やケガに備えたい場合、がん保険も選択肢のひとつです。がん保険とは、がんに特化した保障がついている保険で、さまざまな種類があります。
がん保険には、主に次の4つのタイプがあります。
- 診断給付金タイプ
- 入院給付金タイプ
- 通院給付金タイプ
- 手術給付金タイプ
診断給付金タイプは、がんと診断された時点でまとまった金額が一時金として支払われるタイプです。治療費のほか、仕事を休む期間の生活費に充てたり交通費に使ったりと自由に使えます。
入院給付金タイプは、がんで入院した日数に応じて給付金が支払われるタイプです。長期入院に備えたい方に適しています。
通院給付金タイプは、がんの通院治療にかかる費用をカバーするタイプです。最近は、通院しながらの治療が多くなっており、通院給付金タイプを利用する人が増えています。
手術給付金タイプは、がんの手術を受けた際に支払われるタイプです。手術費用や術後療養費として利用できます。
がん保険を選ぶときは、家族構成や生活スタイル、経済的なリスクにあわせて、どのタイプの保障を重視するかを考えることが大切です。また、主契約に加えて、先進医療特約などをつけることで、より手厚い備えが可能となるでしょう。
医療保険やがん保険選びで迷ったらauフィナンシャルパートナーの「auマネープラン相談」の活用がおすすめです。保険のプロが無料で保険選びをサポートします。ぜひお気軽に保険の悩みをご相談ください。
【働けなくなった場合に備えたい】最低限入っておくべき保険

収入が途絶えることは、家計にとって大きなリスクです。病気やケガによって長期間働けなくなった場合でも、生活費や住宅ローン、教育費などの支出は継続して発生します。公的な障害年金制度はあるものの、受給条件を満たさなければ受給できないうえ、十分な金額が受け取れない可能性もあります。
このような収入減に備えられるのが就業不能保険です。ここでは、働けなくなった場合に備えたいという方におすすめの保険を解説します。
就業不能保険
働けなくなった場合に備えられる保険が就業不能保険です。
病気やケガが原因で長期間働けなくなると、治療費の支出と収入の減少という2つのリスクを抱えることになります。子どもが小さかったり住宅ローンなどの支払いがあったりすると、負担はさらに増え、精神的ダメージも大きくなりがちです。
就業不能保険があれば、再び働けるようになるまで、もしくは保険期間の満了を迎えるまで、長期的な就業不能の状態に備えられます。
なお、保険会社ごとに働けないとみなす条件は異なり、通常「医師の診断にもとづき、所定の期間にわたり全く就労できない状態」が対象となります。
【ライフステージ・年代別】最低限入っておくべき保険

人生には、結婚や子育て、退職といった異なるライフステージがあり、各ステージで直面するリスクや必要となる保障は異なります。そのため、それぞれのステージに適した保険を選んだり、場合によっては見直したりすることが不可欠です。
ここでは、ライフステージや年代別に、最低限入っておくべき保険についてお伝えします。
20〜40代の独身者
20〜40代の独身者が最低限入っておくべき保険としては、医療保険や就業不能保険が挙げられます。
この世代の独身者は、扶養家族がいないため、死亡保障の必要性は比較的低いといえます。ただし、全く不要というわけではなく、万が一の際に両親に迷惑をかけない程度の保障を整えておくと安心です。
一方で重視すべきなのは、病気やケガによる治療費の確保や収入減への備えです。20〜40代は働き盛りですが、病気や事故で入院・通院が長引けば、給与が減少するリスクは誰にでもあります。
このようなリスクに備え、医療保険やがん保険、就業不能保険を中心に検討するとよいでしょう。若いうちに加入すると、保険料が安く抑えられます。
20〜40代の既婚者
20〜40代の既婚者が入っておくべき保険は、終身保険や医療保険、就業不能保険です。万が一の場合に備えて、家族の生活費や教育費を支える必要があるため、死亡保障は欠かせません。
住宅ローンに団体信用生命保険(団信)をつけている場合、住宅ローンの契約者が死亡または所定の高度障害状態になったとき、保険会社がローンの残債を全額弁済してくれます。
住居負担は軽減されますが、生活費や教育費は別途確保しなければなりません。そのため、終身保険だけでなく定期保険も組み合わせて、バランスよく保険に加入することが求められます。
さらに、病気やケガによる収入減のリスクにも備えなければなりません。この世代の既婚者は、住宅ローンや教育費により支出が多いため、収入が途絶えると影響も大きくなりがちです。医療保険やがん保険に加え、就業不能保険も視野に入れるとより安心です。
50代
50代が最低限入っておくべき保険としては、医療保険や就業不能保険が挙げられます。50代は、ライフステージ上では、ひとつの転換期にあたります。
子どもの教育費がピークを迎える一方で、老後資金の準備も並行して進めなければなりません。子どもの独立が近づくと、死亡保障の必要性は低くなります。そのため、この時期は既存の保険を見直すよい機会です。
この世代は、加齢に伴って生活習慣病の発症リスクが高まるため、医療リスクへの備えが必要です。医療保険やがん保険における保障内容や特約を、最新の医療事情にあわせて見直してみましょう。
ただし、50代でも健康状態によっては新規で保険に加入するのが難しい場合もあります。また、年齢が上がることで保険料も割増になる点には注意が必要です。保険の見直しは、健康状態がよいうちに検討したほうがよいでしょう。
就業不能保険については、定年が近づくにつれて、加入の必要性は薄れる傾向にあります。しかしながら、50代はまだ現役世代であり、数年働けなくなるだけでも老後資金面に多大な影響を及ぼしかねません。先々の生活を考え、継続の可否を慎重に判断する必要があります。
60代以降
60代以降が優先すべき保険は、医療保険や介護保険です。定年延長や再雇用制度の普及により、近年は60代でも働き続ける人が増えています。収入があるうちは保険料の支払いが可能ですが、健康状態の変化や退職のタイミングによって加入しにくくなる場合もあるため、早めの見直しが大切です。
すでに子どもが独立している場合は、遺族へ多くの生活費を残す必要性が下がるため、死亡保険金を調整し、老後の医療・介護リスクに対応できる保険に資金を回しましょう。
終身保険については、葬儀費用の準備や相続対策として引き続き活用できます。特に解約返戻金を老後資金として取り崩すなど、資金の流動性を確保する手段としても有効です。
60代は現役と老後の狭間にあり、働きながら老後の準備を進める世代です。今後の収入の見通しを踏まえて、保険料負担を抑えつつ必要な保障を維持することが重要です。
年代ごとのリスクにあわせた保険を見つけたい方は、auフィナンシャルパートナーの「auマネープラン相談」の利用もご検討ください。年齢やライフステージに合った保険選びをプロがサポートいたします。
【男性・女性別】最低限入っておくべき保険

性別によって、直面するリスクやライフイベントは異なります。
男性は、世帯の収入源となるケースが多いため、死亡保障や収入減に備えることが重要です。一方、女性は妊娠・出産や女性特有の病気に対する保障を優先すべきでしょう。特に乳がんや子宮がんなど、女性特有の病気に特化した保険を検討することが大切です。
ここでは、性別ごとに最低限入っておくべき保険について解説します。
男性
男性が最低限入っておくべき保険には、終身保険や就業不能保険が挙げられます。男性は、依然として世帯の主な収入源というケースが多いため、その収入が途絶えると家族の生活基盤が大きく揺らぎます。十分な貯蓄があったり共働きだったりする場合は別ですが、多くのケースにおいては、死亡保障を中心に保険を整えるのが基本といえるでしょう。
特に子どもが小さい時期や住宅ローン、車のローンなどを返済中であれば、残された家族が生活費や教育費に困らないように、定期保険で十分な保障額を確保しておくことが大切です。
また、収入が長期間途絶えるリスクに備える就業不能保険も有効です。病気になり働けなくなると、医療費がかかるうえに収入が減るという二重のリスクが同時に発生します。このようなリスクに対して、医療保険や就業不能保険でしっかりと備えておくことが求められます。
さらに、年齢が上がるにつれて生活習慣病やがんの発症リスクが高まるため、医療保険やがん保険の加入・見直しが欠かせません。長期入院やリハビリが必要となるケースもあり、これらに対応できる保障を用意しておくと治療に専念できます。
女性
女性が入っておくべき保険は、医療保険やがん保険です。女性は男性に比べて平均寿命が長く、医療や介護リスクに直面する期間が長いことが特徴です。加えて、妊娠や出産といったライフイベントもあり、女性特有のリスクに柔軟に対応しなければなりません。
がん研究振興財団が発表している「がんの統計 2025」によると、10代後半〜50代前半までは女性のほうが男性よりもがんの罹患率が高いことが示されています。乳がんや子宮頸がん、卵巣がんなどのリスクに対しては、女性特約つき医療保険の活用が助けとなります。
また、出産に備えて、妊娠前から医療保険に加入しておくこともひとつの選択です。妊娠中に加入を検討しても、加入制限や条件つきの契約になることが多いため、気になることがあれば早めの対策が必要です。
さらに近年では、女性も働きながら家庭を支えるケースが増えています。そのため、状況にあわせて、就業不能保険や所得補償保険を検討してもよいでしょう。
入院などで長期的に働けなくなった場合、育児や介護の負担も考慮しなければなりません。経済的な支えを確保することは、家族にとって大きな意味を持ちます。
さらに女性の場合は、老後への備えも必須です。寿命が長い分、介護や医療にかかる費用は男性よりも多くなる傾向にあります。50歳を過ぎたら、医療保険だけでなく介護保険なども追加で検討しておくとよいでしょう。
参考:公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2025」
最低限入っておくべき保険に加入し万が一に備えよう

過不足なく生命保険に入っておくことは、家族や自分の生活を守るうえで重要です。ライフステージや家族構成、年齢に応じて医療保険に加入したり、就業不能に備えたりしておけば、万が一の際にも安心です。
独身者は、病気やケガによる収入減への備えが中心となるでしょう。既婚者や子育て世代では、家族の生活費や教育費を守る死亡保障が優先されます。50代以降は、老後資金や医療リスクを意識した保険が重要です。60代以降は、医療・介護に焦点を当てた保障へシフトするのが現実的といえます。
また、男性は世帯収入を守るための死亡保障が、女性は特有の病気や長寿への備えがより重視されます。生命保険を検討する場合は、公的保障だけでは不十分な部分を補いつつ、保険料負担を無理のない範囲に収めることが大切です。また、加入して終わりではなく、家族状況の変化に合わせて、随時見直していきましょう。
「auマネープラン相談」では、ご自身に合った保険をプロの目線からご提案が可能です。ご自宅やお近くのカフェなど、希望の場所・時間に無料でご相談いただけるので、お忙しい方もお気軽にご相談ください。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金