老後資金の備え、
大丈夫ですか?
必要があるの?
どうやってるんだろう…
お金のこと、教えて!
人生100年時代ともいわれる現代において、老後に備えた十分な資金を確保するには、
いくら必要なのかと不安に思う方も多いかもしれません。
お金のことを心配せずに老後を過ごせる資金の目安について、昨今の状況も踏まえながら解説していきます。
収入減や物価高騰に関する現状
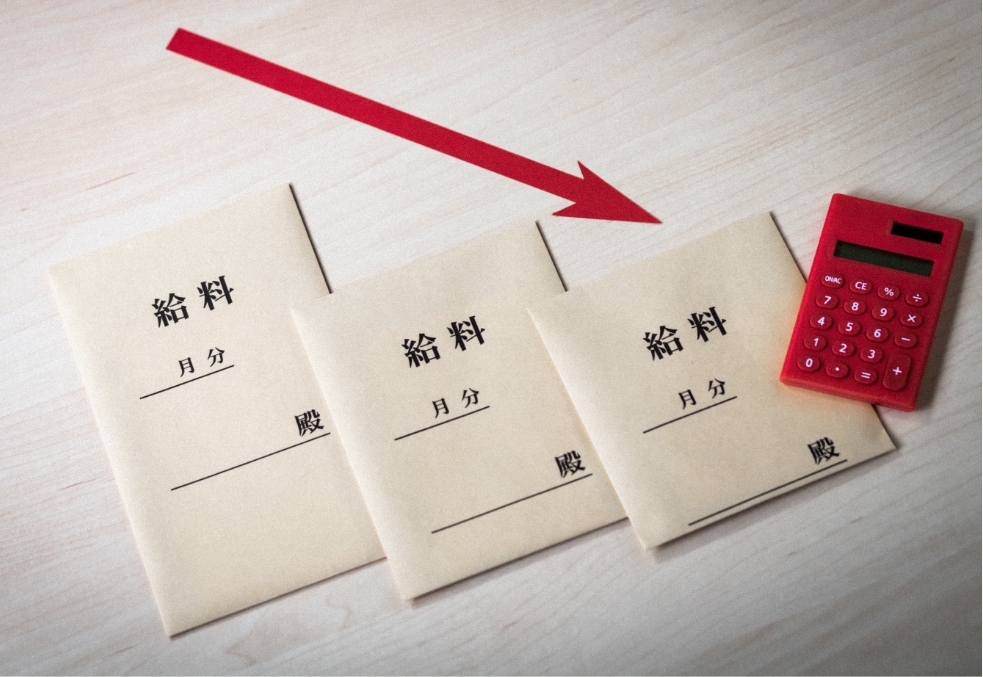
老後資金を用意するうえで把握しておきたいのは「収入減や物価高騰に関する現状について」です。
まずは、収入減について確認していきましょう。2021年に行われた厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の平均賃金は以下のように推移しています。
| 男女計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 2001年 | 30万5,800円 | 34万700円 | 22万2,400円 |
| 2006年 | 30万1,800円 | 33万7,700円 | 22万2,600円 |
| 2011年 | 29万6,800円 | 32万8,300円 | 23万1,900円 |
| 2016年 | 30万4,000円 | 33万5,200円 | 24万4,600円 |
| 2021年 | 30万7,400円 | 33万7,200円 | 25万3,600円 |
男女計の平均賃金を2001年と2021年で比べるとほぼ横ばいですが、男性の平均賃金に至っては20年前よりも下がっています。
加えて、世界情勢の変化による輸入品の国際相場の高騰や、円安による相対的な価格上昇などを理由に、相次ぐ物価高騰も家計に打撃を与えています。
全国の世帯が購入する商品・サービス価格の平均的な変動を表す「消費者物価指数」は、2020年を100で見た場合、2010年の総合指数が94.8であったのに対し、2022年は102.3まで上昇しています。
また、複数の電力会社で電気料金の値上げが発表されるなど、家計に与える支出の負荷は増すばかりです。
必要な老後資金の目安

日本人の平均寿命は、2020年時点で男性が81.56年、女性が87.71年となり、2065年には男性が84.95年、女性が91.35年になると推測されています(※1)。
このように日本人の平均寿命が延びていることもあり、金融庁が公表している2019年6月の金融審議会 市場ワーキング・グループの報告書「高齢社会における資産形成・管理」(※2)では、資産寿命を延ばす必要性が提唱されています。
同報告書では、夫65歳以上、妻60歳以上の無職の二人世帯である場合、年金などで得られる実収入よりも支出のほうが上回り、毎月約5万円の不足が発生すると発表しているのです。
高齢化が進行していることを考慮し、そこから20年生きる場合は約1,300万円、30年生きる場合は約2,000万円の資金が必要とされています。
また、年金受給額が以前に比べて減っている点は、留意しておかなければなりません。「夫婦の基礎年金」と「夫の厚生年金」を合わせた標準的な年金受給世帯の年金額は、2004年が23万3,299円であったのに対し、2022年は21万9,593円に減っています(※3)。
さらに、老齢基礎年金の年金額(40年間保険料を納付した場合の額)も、2004年が6万6,208円であったのに対し、2022年は6万4,816円に減っています(※3)。
こうした状況を踏まえると、老後の生活基盤を安定化させるには、年金以外での収入源の確保や資産形成などがポイントといえるでしょう。
※1 出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書」 ※2 出典:金融庁「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 高齢社会における資産形成・管理」 ※3 出典:厚生労働省「令和4年版 厚生労働白書 資料編」生活費以外にもお金はかかる

食費や水道光熱費、交通・通信費などを含めた生活費以外にも、老後はお金がかかる可能性があります。
例えば病気になった時の治療費用や、介護費用などが挙げられるでしょう。
・治療費用
公益財団法人生命保険文化センターが2019年度に行った「生活保障に関する調査」(※5)によると、治療費用の自己負担額の平均は、直近の入院時では「20.8万円」です。5日未満の自己負担額は平均で「10.1万円」ですが、61日以上では「60.9万円」と、入院日数が長いほど自己負担額も増えています。
・介護費用
さらに、同センターが2021年度に行った「生命保険に関する全国実態調査」(※6)によると、介護費用は、一時的な費用の合計が「平均74万円」、月額では「平均で8.3万円」という結果です。
また、介護期間は「平均61.1ヶ月(約5年1ヶ月)」となっているため、月額平均に介護期間の平均を乗算し、一時的な費用を合計すると、581万1,300円かかる計算になります。公的介護保険制度による費用負担の軽減が見込めるとはいえ、保険を適用するには要介護(要支援)に認定されることが前提で、1~3割は自己負担しなければなりません。
生活費以外にも備えておくべき費用を考慮し、老後の資産構築に向けて早い段階から動き出すことが大切です。
※5 出典:公益財団法人 生命保険文化センター「令和元年度『生活保障に関する調査』」をもとに記載 ※6 出典:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」をもとに記載老後資金のシミュレーション
平均寿命が右肩上がりに延びているのに対し、平均賃金や年金受給額では減額も見られ、
支出に対する収入の不足が懸念されます。
ここでは、ご自身に必要な老後資金を調べるためのシミュレーション方法を紹介します。
老後資金のシミュレーション

老後資金をシミュレーションするには、まず「(B)老後に出ていくお金」を「(A)老後に入ってくるお金」で引いたうえで、残りの生涯年数をかけます。そのうえで、「(C)老後に必要となるお金」を足すと、65歳時点で必要になる老後資金の計算が可能です。
実際に、一般的な夫婦世帯で必要な老後資金をシミュレーションしてみましょう。
老後に入ってくるお金(年間)
公的年金
21万9,593円×12ヵ月=263万5,116円
シミュレーション
上記の項目を計算式に当てはめると、65歳時点で約1,392万円の老後資金が必要という計算になります。ただし、実際はさらに介護費用やお子さまの結婚費用などが上乗せされる可能性もあります。
老後資金を貯めるには?
では、これから老後資金を貯めるにはいったいどのような方法があるのでしょうか。
ここからは、老後資金を貯めるのに適した代表的な方法を4つご紹介します。
方法
01
定期預金

定期預金とは、預入れの時点で1ヶ月~5年などの期間を決めたうえで、銀行やネット銀行へお金を預ける方法のことです。原則的に指定した期間中は預金引出しができない一方、普通預金と比べて金利が高めに設定されているケースが多く、利息を得やすい点がメリットといえます。
また、預金保険制度によって1,000万円までの元本と利息が保証されているため、安心して預け入れることが可能です。定期預金の満期後も、「元利継続型」を選択すれば、元金に利息を加えた金額で継続することになり、預入れが可能となるため効率的に資産運用を行えます。
方法
02
NISA

NISA(少額投資非課税制度)とは、一定の金額内で購入した金融商品の利益に対する税金が、一切かからない制度のことです。
投資商品を購入する際の開設口座は、「一般口座」「特定口座」「NISA口座(一般・つみたて)」などが選べます。NISA口座枠で投資商品を購入すれば、一般・特定口座では運用益に課される20.315%の税率がかからず、非課税のまま利益を受け取れるのです。
なお、NISAは2024年より従来の投資枠から、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に制度が変更されます。現行のNISAを利用している方は自動的に新制度が設定されるため特別な手続きは不要になります。
| 種類 | 非課税保有期間 | 年間非課税枠 | 投資可能商品 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年末 までの NISA |
一般NISA | 5年間 | 120万円 | 上場株式・ETF・REIT・公募株式投信等 |
| つみたてNISA | 20年間 | 40万円 | 一定の投資信託 | |
| ジュニアNISA (20歳未満) | 5年間 | 80万円 | 一般NISAと同じ | |
| 2024年 以降の NISA |
つみたて投資枠 | 無期限化 | 120万円 | 一定の投資信託 |
| 成長投資枠 | 無期限化 | 240万円 | 上場株式・投資信託等 |
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能なため、必要に応じて組み合わせれば、ニーズに合わせた運用が可能となります。
方法
03
iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、20歳以上65歳未満の国民年金加入者であれば、原則的に誰でも加入できる私的年金制度です。毎月の掛け金を自身で決めて積み立て、運用成績に応じた老齢給付金として原則60歳以降に受け取れます。
iDeCoのメリットは、積み立てる掛け金がすべて所得控除の対象となり、所得税・住民税の負担が軽減される点です。
増えた資産に対する税金もかからないため、老後資金の備えとして効率的に運用できるでしょう。受け取り時は、一括もしくは年金での受け取りが選べ、要件ごとに一定金額までは非課税となります。
方法
04
貯蓄型の保険

貯蓄型保険に加入すれば、万が一に備えた「保険」と、将来に向けた「貯蓄」の両方を叶えられます。主な種類としては、終身保険や養老保険などが挙げられます。
貯蓄型保険は満期保険金や解約返戻金が見込めるため、支払った保険料が無駄になりづらい点がメリットです。ただし、保険料は掛け捨て型の保険に比べて割高で、短期で解約した場合は元本割れの可能性もあります。
一方、掛け捨て型保険の場合は保険料が貯蓄型保険に比べて割安で、保障を見直しやすいなどのメリットを持っています。保険の種類はさまざまあるため、世帯ニーズや家計のバランスを見ながら最適な保険商品を選ぶことが大切です。





























