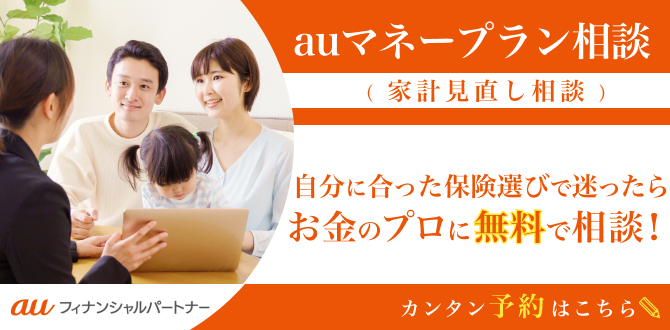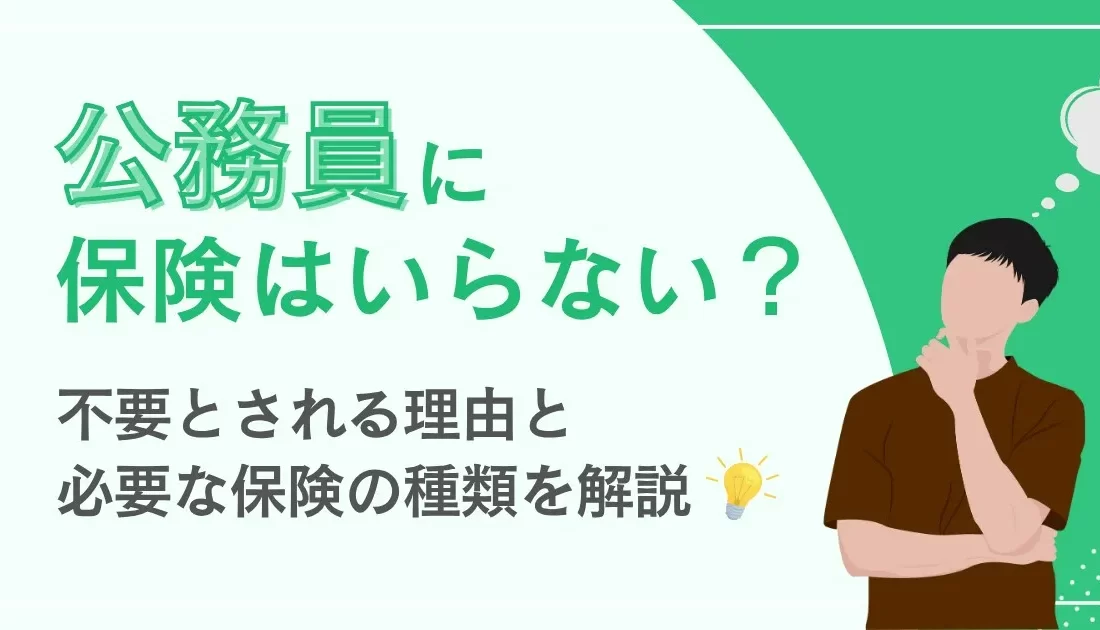保険金受取人とは?権利関係や変更方法、税金についてわかりやすく解説

生命保険には「契約者」と「被保険者」、「保険金受取人」の3者が関わります。
保険金受取人になれるのは、原則として、契約者の二親等内の血族か配偶者のみですが、第三者が受取人になる場合もあります。本記事では、生命保険の権利関係と契約後に受取人を変更する方法について説明します。
また、保険金を受け取ると税金が課せられます。保険金受取人を誰にするかによって、発生する税金の種類が変わるので注意が必要です。その際、どのような税金が発生するのかについてもあわせて説明するので、ぜひご覧ください。
生命保険は保険金受取人・被保険者・契約者の権利関係で成立している
生命保険の契約には、契約を締結して保険料を支払う「契約者」と、保険金支払事由の対象者となる「被保険者」、保険金を受け取る「保険金受取人」の3者が関わります。
例えば、契約者であるAが、Bを被保険者、Cを受取人として生命保険を契約したとします。その場合、Bが死亡あるいは保険契約に定められた状態になったときには、Cが保険金を受け取ります。このCにあたる人が「保険金受取人」です。
保険金受取人の変更の可否は保険会社の規定による
生命保険の契約締結後、保険会社が規定する範囲内で、保険金受取人を変更することができます。全ての保険会社で保険金受取人の変更ができるとは限らず、変更できる範囲も会社によって異なるため注意しましょう。
変更できるのは保険期間(保険が有効な期間)のみです。すでに保険金支払事由が発生した後では、変更できません。例えば、死亡保険金の場合、被保険者が死亡した後で保険金受取人を変更することはできません。
また、保険金受取人を変更するときは、被保険者の同意が必要です。変更する前に被保険者に確認しておきましょう。
遺言で保険金受取人を変更できる場合がある
2010年4月以降に締結した保険契約は、遺言によって保険金受取人を変更することが可能です。ただし、この場合も契約者が被保険者の同意を得ていることが条件となります。また、遺言が法律上有効であること、保険金受取人がまだ保険金を受け取っていないことも条件となります。
生命保険は保険金受取人を誰にするかによって税金が変わる

保険契約者と受取人の関係によって、保険金を受け取ったときの税金の種類が変わります。まずは以下をご覧ください(※)。同じ記号は同一人物をさします。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 保険金に課せられる税金 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
| A | B | A | 所得税 |
(※)出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をもとに筆者作成
以下では、税金の種類と課税対象額の計算方法、税制優遇方法について紹介します。
相続税がかかる場合
契約者と被保険者が同一人物で、保険金受取人のみ異なる場合は、保険金は相続税の課税対象です。
保険金から「500万円×法定相続人の人数」を差し引いた部分に対して相続税が発生するため、保険金受取人のみが異なるときは、保険金の金額を「500万円×法定相続人の人数以下」に設定しておくと税金対策になります(※1)(※2)。
ただし、保険金受取人が相続人でない場合は遺贈扱いとなります。この場合は、相続税の課税対象とはなるものの、税額が2割増しになるので注意が必要です(※3)。
また、一時金ではなく年金として受け取るときは、相続税ではなく所得税の課税対象(年金を受け取る権利は相続税の課税対象)となる点にも注意が必要です。
(※1)出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
(※2)出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
(※3)出典:国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
贈与税がかかる場合
契約者と被保険者、保険金受取人のすべてが異なるときは、贈与税の課税対象となります。110万円を超えた部分に対して贈与税が発生します。ただし、保険金以外にも同じ年にほかから財産を受け取った場合は、すべての贈与を合算して110万円を除いた金額が課税対象です(※1)。
直系尊属から成人卑属に対する贈与は、税率が低い「特例贈与」が適用されることがあります。例えば、祖父母から18歳以上の孫、父母から18歳以上の子に保険金が贈与される場合は、特例贈与となります。
なお、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税にできます。相続時精算課税制度を利用するときには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告書を提出することが必要です(※2)。
ただし、相続時精算課税制度を選択するとその後「暦年贈与」の適用を受けることはできず、また「暦年贈与」へ戻すことができなくなるため注意しましょう。
(※1)出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
(※2)出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
所得税がかかる場合
契約者と保険金受取人が同一人物で、被保険者のみ異なる場合は、保険金は所得税の課税対象です。保険金から保険料総額を差し引き、差額が50万円以上のときは「差額×1/2」が一時所得となり、課税対象となります。給与所得などのほかの所得と合算し、課税総所得額を求めてから所得税額を算出します(※)。
死亡保険金を年金として受け取るときは、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額を雑所得とします。この場合も、一時所得と同じく、給与所得などのほかの所得と合算して総所得を求めて所得税額を算出します。
(※)出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
途中解約により所得税がかかる場合がある
今までに支払った保険料よりも解約返戻金が多い場合、差額が50万円以上のときは「差額×1/2」が所得税の課税対象となります(※1)。
また、保険料を一時払いし、5年以内に解約している場合は、解約返戻金と保険料の差額に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。ただし、契約から年数が経っていないときは解約返戻金も少ないため、源泉徴収されることはあまりないと考えられます(※2)。
しかし、解約返戻金が少ないということは、保険料と解約返戻金の差額分、損失が生じていることでもあります。短期間で解約する必要が生じないように、慎重に検討してから保険契約を締結しましょう。
(※1)出典:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
(※2)出典:国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」
生命保険金の受取人に悩んだらauフィナンシャルパートナーに相談を

生命保険では、誰を保険金受取人にするかによって税金の種類や税額が異なります。また、保険金額によっても税制優遇方法は異なるため、生命保険の契約は簡単とはいえません。
保険契約も含めた家計の見直しは、ぜひauフィナンシャルパートナーにご相談ください。お金のプロであるファイナンシャルプランナーが、お金の悩みの解決をサポートいたします。
どんなことが相談できる?
auフィナンシャルパートナーに寄せられているマネープラン相談は、例えば以下のようなものです。
-
- 家計管理
- 貯蓄が増えないのは家計管理が問題?
- 今の家計で将来の資金は大丈夫?
-
- 老後資金
- 老後はいくらあれば安心?
- 効率的な老後資金の貯め方を知りたい
-
- リスク管理
- 保険ってよくわからない、そもそも必要?
- 私に合った保険か調べて欲しい
-
- 住宅資金
- 住宅ローン返済計画など、最適な選択肢を知りたい
- 購入すべきベストなタイミングはいつ?
-
- 教育資金
- 希望の進路に進ませるにはいくら必要?
- 効率的な資金準備の方法を知りたい
-
- 資産形成
- 老後資産を形成したい
- 早期退職のため資産形成したい
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが一人ひとりに合わせたキャッシュフロー表を作成し、お金に関するお悩み解決をサポートいたします。
auフィナンシャルパートナーなら
安心の品質!
-
お客さま満足度93.9%
私たちのサービスを実際に受けたお客さまの満足度は93.9%の評価を頂いています。
身近な節約から資産形成まで、お金の悩みは人それぞれ。さらにライフステージによって悩みも変化します。
お金のプロの視点から一人一人が安心し、豊かに過ごすために何度でも無料でアドバイスいたします。 -
累計相談件数15万件
当社は開業から5年で累計相談件数が15万件以上のサービスを提供してきました。
あなたが初めてではありません。
お金のプロとしての知見、そして15万件以上のご相談実績から安心してお金の悩みをご相談いただけると思います。 -
全国対応
お客さまがご都合の良い場所まで、私たちがお伺いします。
お金の相談をするために時間をかけて移動したり、慣れない場所で相談する必要はありません。
安心できる場所で、落ち着いて、お金に関するお悩みをお話いただけます。
気兼ねなくご要望をお聞かせください。
auフィナンシャルパートナーへの
ご相談の流れ
-
Step.1 相談予約
「予約ボタン」より必要事項とお電話希望時間帯、相談内容をお申込ください。
-
Step.2 予約のご確認
ご相談の日時、場所、相談内容などをオペレーターがお電話で確認させていただき、予約は完了となります。
-
Step.3 ご相談
お客さまのお悩みを解決するため、お金のプロに何度でも無料でご相談いただけます。
まとめ
生命保険は、誰を保険金受取人とするかによって税金の種類や税額が異なります。また、受取人によって税制上の優遇を受けられるかどうかも異なるため、慎重に保険契約を締結する必要があります。
生命保険についてのお悩みは、ぜひauフィナンシャルパートナーにご相談ください。プロの視点から税制上のメリットなどをご説明いたします。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金