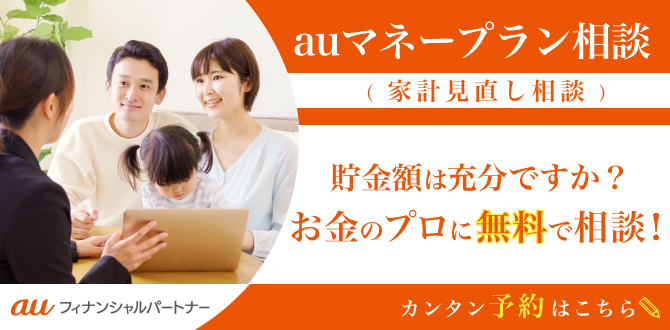40代の平均貯金額はいくら?老後資金の準備方法も具体的に紹介

40代になり、将来に向けた老後資金の準備を考えはじめる人は多いかもしれません。介護保険料の負担がはじまることも、老後を意識させる要素のひとつです。
いざ年金生活がはじまったときに貯蓄額が不十分だと、生活が苦しくなる可能性があります。そこから収入を増やそうと思っても、実際には困難であることがほとんどでしょう。一般的に、40代はどれくらい貯金しているのでしょうか。
本記事では40代の貯金額について、実際の平均額、中央値や目安を解説します。
準備は早いに越したことはありません。40代のうちから、老後資金の準備をスタートしましょう。
40代の平均貯金額と中央値とは
世間の40代はどれくらいのお金を貯めているのでしょうか。次の項では、40代の平均貯金額と中央値を解説します。
中央値とは、順に並んだデータのちょうど中央にある値のことで、大きく外れた値の影響を受けにくいことが特徴です。データにばらつきがあってもより実感に近い数字になるとされています。
40代単身者の平均貯金額と中央値
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、40代単身者世帯の金融資産保有額は、全体の平均で559万円、中央値が47万円でした(※)。
金融資産を保有していない世帯を除くと964万、中央値は500万となっています(※)。
平均値よりも中央値が大幅に少ないことから、一部の金融資産保有額が多い世帯が全体の平均値を押し上げていることがわかります。
(※)出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」
40代二人以上世帯の平均貯金額と中央値
同調査の二人以上世帯調査では、全体の平均が889万円、中央値が220万円です(※)。
金融資産を保有していない世帯を除くと平均が1,236万円、中央値は500万円となっています(※)。
単身者世帯同様、平均値よりも中央値が大幅に少ないことから、一部の金融資産保有額の多い世帯が、全体の平均値を押し上げていることがわかります。また、単身者世帯と比較すると、二人以上の世帯の方が貯金額も多いです。
(※)出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
40代が考える老後の不安や生活費
40代は老後に対してどのような不安を持っているのでしょうか。
2022年に行われた(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によれば、老後に対する不安を感じている男性は88.3%、女性は93.6%でした(※)。不安の内容や希望する生活水準を詳しく紹介します。
(※)出典:生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
老後不安の内容
40代男女に老後に対する不安を尋ねたところ、男女ともに「公的年金だけでは不十分」を挙げる方が最も多く見られました。
男性の2位は「退職金や企業年金だけでは不十分」、女性の2位は「日常生活に支障が出る」であることから、経済的な面を不安に感じる男性が多いのに対し、女性は身体的な面の不安を強く感じていると考えられます。
| 男性 | 女性 | |
| 1位 | 公的年金だけでは不十分 | 公的年金だけでは不十分 |
| 2位 | 退職金や企業年金だけでは不十分 | 日常生活に支障が出る |
| 3位 | 日常生活に支障が出る | 自助努力による準備が不足する |
| 4位 | 自助努力による準備が不足する | 退職金や企業年金だけでは不十分 |
| 5位 | 仕事が確保できない | 仕事が確保できない |
老後に希望する生活水準
老後の生活は現在よりもつつましい生活を希望する方が、男女ともに多く見られました。40代は、20代や30代と比べてつつましい生活を希望する人が増える傾向が見られます。
| 経済的に豊かな生活 | 同じ程度の生活 | つつましい生活 | わからない | |
| 男性全体 | 2.8% | 28.4% | 61.6% | 7.3% |
| 20歳代 | 5.1% | 23.0% | 56.2% | 15.7% |
| 30歳代 | 2.9% | 26.2% | 60.4% | 10.5% |
| 40歳代 | 2.7% | 20.8% | 71.7% | 4.8% |
| 50歳代 | 2.0% | 22.1% | 70.1% | 5.9% |
| 女性全体 | 1.9% | 25.1% | 65.8% | 7.2% |
| 20歳代 | 5.2% | 26.2% | 49.5% | 19.0% |
| 30歳代 | 2.5% | 29.0% | 60.7% | 7.9% |
| 40歳代 | 1.3% | 16.5% | 74.7% | 7.5% |
| 50歳代 | 2.0% | 16.5% | 77.0% | 4.5% |
老後に必要と思う生活費
40代が老後に必要だと思う最低日常生活費は、平均23.1万円でした。4人に1人以上が20万~25万円未満は必要だと考えています。
| 老後の最低 日常生活費 |
15万円未満 | 15~20万円未満 | 20~25万円未満 | 25~30万円未満 | 30~40万円未満 | 40万円以上 | わからない | 平均(万円) |
| 全体 | 4.9% | 9.2% | 27.5% | 14.4% | 18.8% | 2.8% | 22.5% | 23.2 |
| 男性 | 5.7% | 9.6% | 27.9% | 14.0% | 17.4% | 2.5% | 22.9% | 22.8 |
| 女性 | 4.2% | 9.0% | 27.2% | 14.7% | 19.8% | 3.0% | 22.1% | 23.5 |
| 40歳代 | 3.7% | 9.0% | 31.1% | 15.7% | 19.6% | 2.4% | 18.4% | 23.1 |
40代が考える、ゆとりのある老後生活のために上乗せしたい金額は15.2万円でした。また、上乗せした金額は、旅行やレジャーに使いたいと考えている方が60.0%、日常生活費の充実には48.6%、趣味や教養には48.3%の方が使いたいと考えています。
公的年金に対する不安
公的年金だけでは老後資金を賄えないと思う40代は男性86.9%、女性86.5%もいました。老後資金について、個人的に準備する必要性を強く感じている方が多いと考えられます。
老後資金の備え
老後資金について、貯金で備えている40代は男性46.9%、女性44.0%います。また、個人年金保険などの方法で備えている方も4割以上見られました。その一方で、約3割の方が老後資金の準備をしていないと回答しています。
| 老後資金の準備方法 | 個人年金保険・変額個人年金保険や生命保険 | 損保の年金型商品 | 預貯金 | 有価証券 | その他 | 準備していない |
| 40代男性 | 43.5% | 12.3% | 46.9% | 10.7% | 0.0% | 28.5% |
| 40代女性 | 43.1% | 9.0% | 44.0% | 8.1% | 0.9% | 31.6% |
40代からはじめる老後資金の準備

次の項では、実際に老後資金を増やすために、今すぐにでもはじめられる方法をいくつか紹介します。
・家計簿をつける
・家計の支出を削減する
・iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する
・NISA(少額投資非課税制度)を利用する
・資産運用を検討する
・国民年金の追納や付加保険料納付を行う
それぞれ詳しくみていきましょう。
家計簿をつける
老後資金準備の前段階として、まず収入と支出の把握が大切です。収支のバランスを知って、家計をコントロールしましょう。
家計簿は手書きのほか、表計算ソフトや専用アプリなどを活用する方法があります。レシートを読み取って自動入力できる機能が搭載されているものもあり、こうしたツールを使うことで手間が省けます。
家計簿は継続してつけることが重要です。無理なく家計を管理できるよう、自分のやりやすい方法を見つけましょう。
家計の支出を削減する
家計改善の策として、収入を増やすことができるのであれば良いですが、なかなか現状では難しい家庭も多いと思います。
しかし、収入アップが見込めなくても支出を減らすことで改善は図れます。家計簿をつけて全体の支出がわかったら、削減できる部分がないかチェックしましょう。
生活費は固定費と変動費に大別されますが、まずは見直しやすい固定費からはじめるのがおすすめです。
【固定費】
・住居費は住宅ローンの借換え・賃貸物件であれば家賃減額の交渉を検討する
・通信費はスマートフォンやインターネット回線のプランやオプションを見直す
・保険は保障内容を見直す。通常、ライフステージの変化に応じて必要な保障内容も変わるため、不要な保障があれば外す
・課金アプリやサブスクリプションなど、使用していない・または使用頻度の低いサービスがあれば解約を検討する
【変動費】
・電気代・ガス代は契約内容を見直すことで料金が安くなる場合がある。割安なセットプランや特典のつく他社乗り換えも視野に入れる。また、エアコンなどの家電は省エネモードがあれば無理のない範囲で活用する
・水道代は、水やお湯を出しっぱなしにせず節水に努める。節水シャワーをはじめ、エコグッズを利用するのも良い
iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する
iDeCoは、税制優遇を受けながら積み立てで資産を運用する制度です。
掛金は所得控除の対象となるため所得税・住民税が軽減されるメリットがあり、さらに運用収益も非課税です。
元本と収益の合計を年金として受け取るほか、一時金としてまとめて受け取ることも可能です。ただし、原則60歳までは引き出すことができないため注意が必要です。
また、iDeCoでは自分で投資商品を選んで運用しますが、選んだ商品の運用結果によっては元本割れの可能性もあります。加入する前に、商品の知識は得ておくようにしましょう。
NISA(少額投資非課税制度)を利用する
NISA(少額投資非課税制度)は少額から投資ができて、得た利益に対して税金がかからない制度です。2024年から新しくなった制度により、1,800万円までの投資が非課税となったことに加え、非課税保有期間も有期から無期限に変わりました。
基本的には長期の運用でリターンを得ることが前提ですが、運用商品を売却すれば資金をいつでも引き出すことができます。ただし手続きには数日かかり、即日現金化できるわけではないので注意しましょう。
資産運用を検討する
使う予定のない余裕資金がある人は、iDeCo・NISA以外の投資も検討してみましょう。
資産運用の方法は多数ありますが、一般的にリターンの大きい投資方法はリスクも大きくなります。配当金・金利・利回りと経済的な知識も身につけつつ、自分にあった投資を選びましょう。
主な投資の種類と特徴
| 個人年金保険 | 支払った保険料を原資として将来の年金を準備する民間の保険商品 |
| 投資信託 | 投資の専門家ファンドマネージャーに運用を任せ分配される利益を受け取る |
| 株式 | 株式会社が発行する株式を売買して利益を得るほか、配当による利益を受け取る |
| 債券 | 国や地方自治体、企業などが発行する債券に投資する |
| 外貨預金 | 日本円を外国通貨に換えて預け入れる預金 |
| 金 | 設定した金額分の金を積立購入する |
投資をはじめるにあたっては、将来のライフイベントをしっかり把握し、不測の事態に備える手元資金は残しておくようにしましょう。
国民年金の追納や付加保険料の納付を行う
過去に年金の未納があれば、将来の受け取り額が減ってしまいます。追納できる期限内に忘れず納付するようにしましょう。
免除や減免、特例の措置を受けた場合も、同様に追納すれば年金を増やすことができます。
国民年金第1号被保険者であれば、国民年金の付加保険料の納付でも将来の年金を増額できます。
付加保険料は、通常の定額保険料に月額400円を上乗せして支払います。この付加年金額は、200円×付加保険料を納めた月数で計算されます。また、前納による割引もあります。
40代の家計の悩みや老後資金の相談はauマネープラン相談(家計見直し相談)がおすすめ
40代の平均貯金額のデータを見て、平均より少なかった方、多かった方、多かったが不安は残る方、さまざまな方がいらっしゃると思います。
もし家計についてプロに相談してみたい場合は、auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談(家計見直し相談)がおすすめです。auマネープラン相談では、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)が、お金に関するお悩み解決を無料でサポートします。
老後資金をはじめ家計に関して相談したい方は、一度プロ目線のアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。iDeCoについても相談可能(※)です。
(※)具体的な投資銘柄の推奨や投資助言を行うことはできませんが、制度に関する疑問や加入にあたってのお悩みには親身になってアドバイスを提供します。
40代からの老後資金準備
40代の貯金額や老後資金の準備手段を紹介してきましたが、まずは自分の家計に目を向け、将来の計画をたてることが大切です。
auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談ではファイナンシャルプランナーによる家計改善のアドバイスが受けられます。相談に費用はかかりませんので、こういったサービスもうまく活用して家計改善を図りましょう。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金