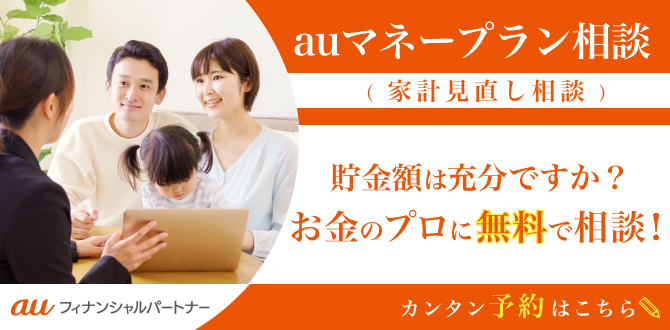大学の学費はいくら?保護者と学生に向けて必要な資金を解説

大学の学費は、入学前に把握しておくべき重要な情報です。まとまった費用を定期的に納めるため、おおよその金額を把握し事前に備えておく必要があります。
大学生活を送るにあたっては入学料・授業料以外にもお金がかかりますが、この費用に対して、さまざまな支援制度があることをご存じでしょうか。奨学金をはじめ、貸付制度やローンなど、大学生活にかかる費用の工面をサポートする制度を知っておいて損はありません。
本記事では、国公立大学と私立大学それぞれの学費や、学費以外にかかるお金、そして支援制度について解説します。
大学の学費はいくらかかる?国公立と私立の違い
大学の学費としては、国公立・私立ともに「入学料」と「授業料」があります。私立ではさらに「施設設備費」が加わるのが一般的です。通常、これらの合計が初年度納入金となります。
ここでは、国公立と私立に分けて学費の平均と中央値を紹介します。
中央値とは、順に並んだデータのちょうど中央にある値のことで、大きく外れた値の影響を受けにくいことが特徴です。データにばらつきがあっても、より実感に近い数字になるとされています。
国公立大学の学費は?平均値と中央値
まずは国立大学の学費をみていきましょう。
文部科学省の平成22年度調査結果によると、国立大学昼間部の入学料は282,000円、授業料は535,800円で初年度納入金が817,800円です(※1)。
次に公立大学ですが、多くの公立大学では学生や保護者の住所によって入学料が異なります。文部科学省の2022年度調査結果によると、大学指定の地域内での平均は入学料が226,856円、授業料が536,195円、初年度納入金が763,051円。地域外では入学料が389,125円、初年度納入金が925,320円です(※2)。
中央値でみると、地域内で入学料232,000円、授業料が535,800円。地域外では入学料が366,600円となり、初年度納入金は825,600円です。
国公立大学の学費は、次の項で紹介する私立大学よりも低い傾向にあります。
(※1)出典:文部科学省「平成22年度国立大学の授業料、入学料及び検定料の調査結果について」
(※2)出典:文部科学省「2022年度学生納付金調査結果」
私立大学の学費は?平均値と中央値
それでは次に、文部科学省の調査結果を参考に、私立大学の学費をみていきましょう。
令和3年度の私立大学入学に係る初年度学生納付金の平均は、入学料が245,951円、授業料が930,943円、中央値では入学料が252,932円、授業料が1052,574円です(※)。
また、多くの私立大学では、初年度納入金として入学料・授業料に施設設備費が加わります。
この施設設備費の平均は私立大学で180,186円、私立短期大学で166,603円です。一般的に、私立大学の学費は国公立大学よりも高い傾向にあることがわかります。
(※)出典:文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
大学で入学料・授業料の学費以外にかかる費用は?
大学生活を送るにあたり、入学料・授業料以外ではどのような費用がかかるのでしょうか。
入学までにかかる費用としては、受験料や受験のための交通費・宿泊費、予備校の授業料などがあります。そして入学後の費用には、教材費、場合によりサークル活動費や留学費などがあります。
寮やアパートに住む場合は、賃貸住宅の契約金、引越し費、家賃、食費、水光熱費、通信費も必要です。いざ支払う段階になって慌てることのないよう、学費以外の費用についても事前に見積もっておくことが大事です。
大学の学費に支援制度はある?

多くの場合、大学の学費はまとまった額を定期的に捻出する必要があり、家計にも大きな影響を及ぼします。しかし、大学生活にかかる費用には支援制度もあります。
代表的な制度は、以下の2つです。
・高等教育の修学支援新制度
・奨学金制度
学費でお悩みの家庭はこのような支援制度を利用することも選択肢のひとつです。
高等教育の修学支援新制度
「高等教育の修学支援新制度」とは、教育格差の解消や若者の負担軽減を目的に、2020年にスタートした国による新しい制度です。
成績や年齢、世帯収入を含む条件を満たした学生が対象で、学費の減免や、日本学生支援機構(JASSO)の給付型(返済不要)奨学金を受けることができます。支援内容は条件により異なりますが、申請は進学前から行うことができます。
ただし、申請できるのは対象校のみです。まずは、志望校や在学中の学校が対象かどうかを確認する必要があります。
奨学金や貸付制度・教育ローンという方法も
学費を準備するにあたり、奨学金や教育ローンを借りるという方法もあります。
奨学金には返済不要の給付型と返済が必要な貸与型があり、奨学金事業を行う代表的な団体としては日本学生支援機構(JASSO)があります。日本学生支援機構(JASSO)では、前項で紹介した「高等教育の修学支援新制度」の給付型奨学金を受けている場合でも、貸与型とあわせて利用が可能です。
このほか、自治体による奨学金や貸付制度、大学独自の奨学金、私財による奨学金もあります。
教育ローンには、国によるものと、民間の金融機関が取り扱うものがあります。それぞれ借り入れできる額や金利に差があるため、収入や必要な金額にあわせて選ぶようにしましょう。
学費や寮費の減免など大学独自の制度
大学独自で奨学金以外の支援制度を行っている場合もあります。
学費や寮費の減免、分納や延納の許可と、支援内容は大学によって多岐にわたります。
成績や収入に条件がある場合がほとんどですが、該当する場合はこうした制度の活用も検討してみましょう。
大学生活の家計を助ける制度
これまで紹介してきた方法以外にも、大学生活の家計を助ける制度があります。直接お金がもらえるわけではありませんが、生活費をサポートする手段として知っておくとよいでしょう。
勤労学生控除
アルバイトで課税所得が発生するほど働いた場合、勤労学生控除を受けることで所得税が減税されます。
この控除を受けるには、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生の欄をチェックしておく必要があります。このチェックを入れておくことで、年末調整が行われる段階で所得控除が適用されます。
国民年金保険料の学生納付特例制度
日本に住む20歳以上の人は国民年金の被保険者として保険料を納付する義務がありますが、学生の場合は申請を行うことによって納付が猶予されます。これが「国民年金保険料の学生納付特例制度」です。
住民登録をしている市区町村役場もしくは年金事務所で手続きを行えば、在学中は保険料の納付が猶予されます。猶予された分は10年以内であれば遡って追納ができます。追納を行えば将来受け取る年金の額を増やすことが可能です。
大学の学費支援制度の対象となる条件とは?
大学で「高等教育の修学支援新制度」を利用するには、その大学がまず対象校であることが前提となります。そして、制度の対象者となる条件は以下のとおりです(※)。
・世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯、または非課税世帯に準ずる世帯の学生。年収目安は「両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合」で380万円以下。資産は生計維持者が2人の場合 2,000万円未満、生計維持者が1人の場合 1,250万円未満)
・進学先で学ぶ意欲がある学生であること
各種奨学金はそれぞれ条件が設定されていますが、代表的な日本学生支援機構(JASSO)の対象者となる条件は「高等教育の修学支援新制度」と同じです。そのほかの奨学金や貸付制度は各団体に確認するようにしましょう。
(※)出典:文部科学省「高校生の皆さんへ」
教育資金の相談・シミュレーションはauマネープラン相談がおすすめ
学費は家計に大きな影響を与えます。学資保険で教育資金を備えていても、実際に足りるかどうか不安のある方も多いと思います。
教育資金の準備やシミュレーションについては、プロに相談する方法も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談では、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)から、家計に対するアドバイスを無料で受けることができます。給与が低水準のまま物価上昇も著しい昨今、教育資金だけでなく家計全体を見直して改善を図るのがおすすめです。
お客さまのご都合にあわせた時間・場所で相談でき、FPはお客さまの状況を詳しくヒアリングしプロの目線でお金のお悩み解決をサポートします。
どんなことが相談できる?
auフィナンシャルパートナーに寄せられているマネープラン相談は、例えば以下のようなものです。
-
- 家計管理
- 貯蓄が増えないのは家計管理が問題?
- 今の家計で将来の資金は大丈夫?
-
- 老後資金
- 老後はいくらあれば安心?
- 効率的な老後資金の貯め方を知りたい
-
- リスク管理
- 保険ってよくわからない、そもそも必要?
- 私に合った保険か調べて欲しい
-
- 住宅資金
- 住宅ローン返済計画など、最適な選択肢を知りたい
- 購入すべきベストなタイミングはいつ?
-
- 教育資金
- 希望の進路に進ませるにはいくら必要?
- 効率的な資金準備の方法を知りたい
-
- 資産形成
- 老後資産を形成したい
- 早期退職のため資産形成したい
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが一人ひとりに合わせたキャッシュフロー表を作成し、お金に関するお悩み解決をサポートいたします。
auフィナンシャルパートナーなら
安心の品質!
-
お客さま満足度93.9%
私たちのサービスを実際に受けたお客さまの満足度は93.9%の評価を頂いています。
身近な節約から資産形成まで、お金の悩みは人それぞれ。さらにライフステージによって悩みも変化します。
お金のプロの視点から一人一人が安心し、豊かに過ごすために何度でも無料でアドバイスいたします。 -
累計相談件数15万件
当社は開業から5年で累計相談件数が15万件以上のサービスを提供してきました。
あなたが初めてではありません。
お金のプロとしての知見、そして15万件以上のご相談実績から安心してお金の悩みをご相談いただけると思います。 -
全国対応
お客さまがご都合の良い場所まで、私たちがお伺いします。
お金の相談をするために時間をかけて移動したり、慣れない場所で相談する必要はありません。
安心できる場所で、落ち着いて、お金に関するお悩みをお話いただけます。
気兼ねなくご要望をお聞かせください。
auフィナンシャルパートナーへの
ご相談の流れ
-
Step.1 相談予約
「予約ボタン」より必要事項とお電話希望時間帯、相談内容をお申込ください。
-
Step.2 予約のご確認
ご相談の日時、場所、相談内容などをオペレーターがお電話で確認させていただき、予約は完了となります。
-
Step.3 ご相談
お客さまのお悩みを解決するため、お金のプロに何度でも無料でご相談いただけます。
大学の教育費を計画的に準備しよう
大学の学費や支援制度について事前に知っておくことで、実際にどの程度の教育資金が必要であるのかプランもたてやすくなります。
プロのアドバイスを受けるなどさまざまな手段も活用しながら教育資金を計画的に準備しましょう。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金