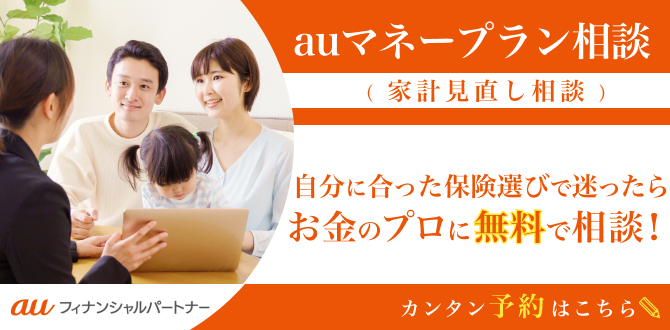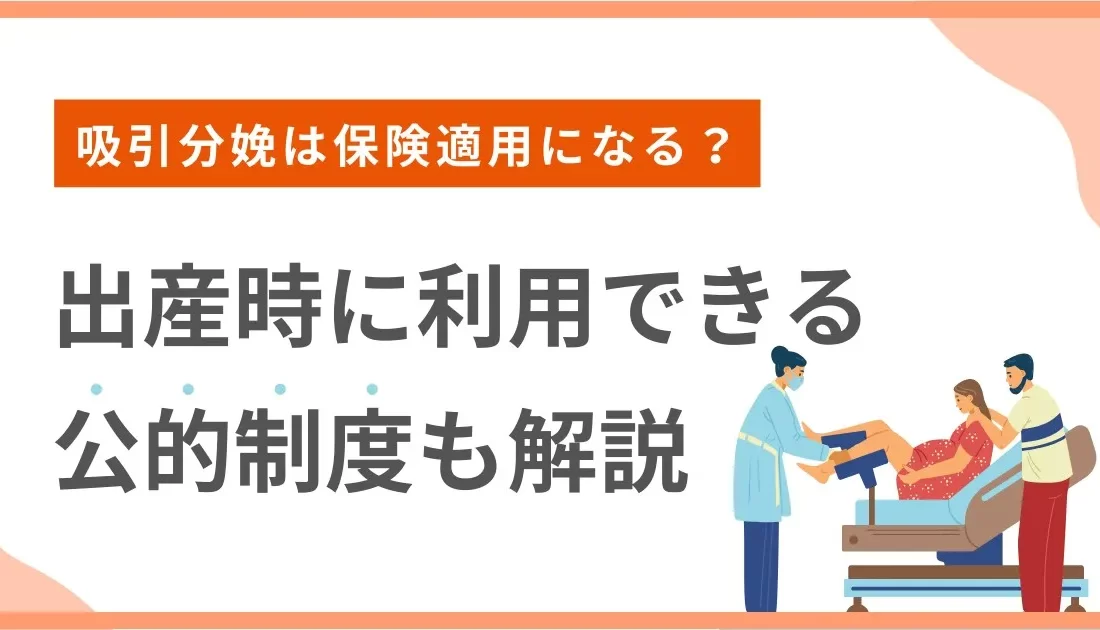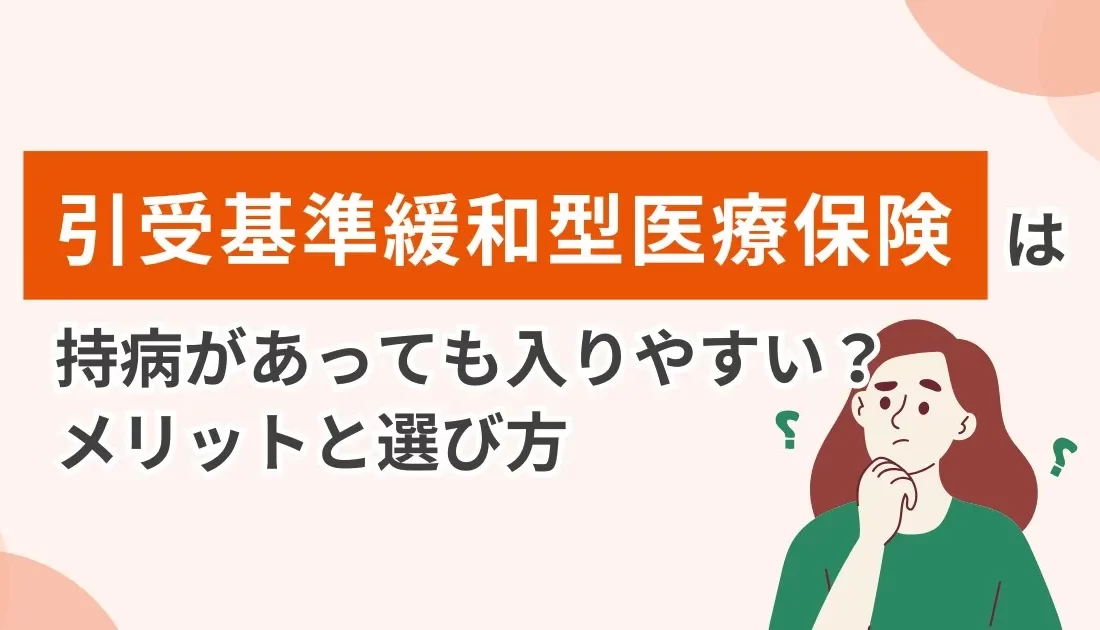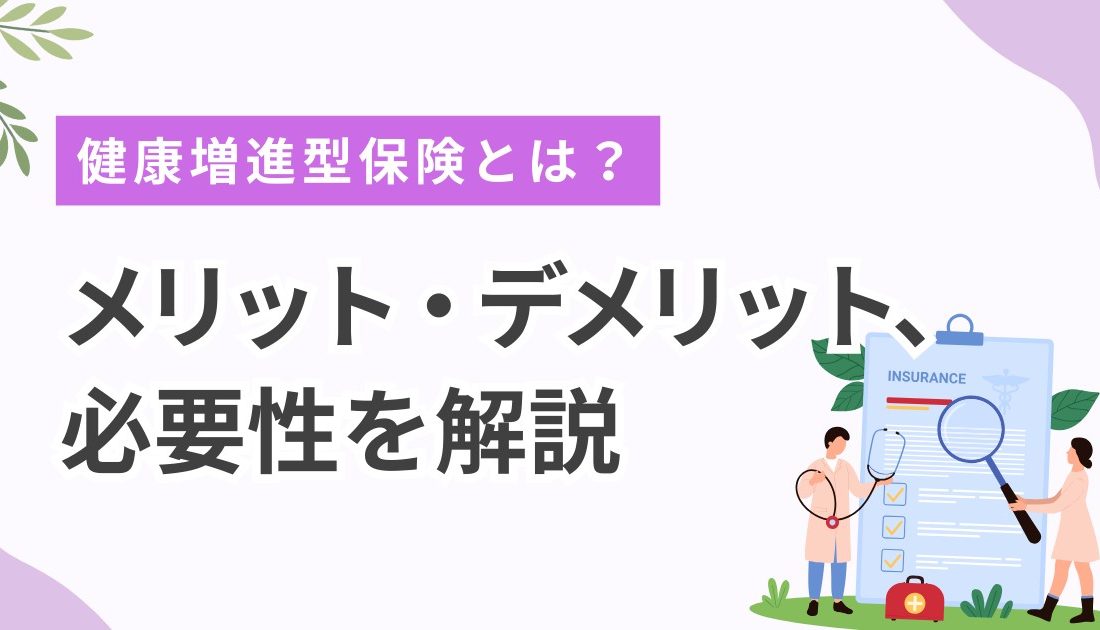学資保険のメリットや注意点とは?選ぶときのポイントも解説

独り立ちするまで、子どもの教育費は長年にわたって必要であり、家計に与える影響が大きい費用です。教育資金は、子どもの進学を見据え、あらかじめ計画的に準備しておくことが大切です。
支払う段階になってから「足りない」と慌てるような事態は、何としても避けなければなりません。教育資金を準備する方法としては、学資保険が挙げられます。学資保険は「子ども保険」とも呼ばれていますが、どのような保険商品なのでしょうか。
本記事では、平均的な教育費のデータをはじめ、学資保険の仕組みやメリット・注意点を解説します。
いざというときに「教育資金が足りない」と困らないよう、学資保険を活用して子どもの将来に備えましょう。
将来の教育資金に備える学資保険
まずは、文部科学省の調査結果を用いて、教育資金のおおまかなデータを解説します。
幼稚園から大学までに必要な教育資金の目安は次のとおりです。
・子ども一人あたりの年間学習費総額
| 公立 | 私立 | ||
| 幼稚園 | 16.5万円 | 幼稚園 | 30.9万円 |
| 小学校 | 35.3万円 | 小学校 | 166.7万円 |
| 中学校 | 53.9万円 | 中学校 | 143.6万円 |
| 高校 | 51.3万円 | 高校 | 105.4万円 |
| 大学 | 481.2万円 | 大学(文系) | 689.8万円 |
| – | – | 大学(理系) | 821.6万円 |
(小数点第二位以下は四捨五入)
(※)出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」
日本政策金融公庫「令和元年度 教育費負担の実態調査結果」
上記の資料を元に筆者作成
・平均初年度納入額
| 授業料 | 入学料 | 施設設備費 | 合計 | |
| 私立大学 | 93.1万円 | 24.6万円 | 18万円 | 135.7万円 |
| 私立短期大学 | 72.3万円 | 23.8万円 | 16.7万円 | 112.8万円 |
| 国公立大学 (地域内) |
53.6万円 | 22.7万円 | – | 76.3万円 |
| 国公立大学 (地域外) |
53.6万円 | 38.9万円 | – | 92.5万円 |
(小数点第二位以下は四捨五入)
(※)出典:文部科学省「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果」
文部科学省「2022年度学生納付金調査結果」
上記の資料を元に筆者作成
上記結果のとおり、教育資金は家計にとって大きな負担となる費用です。
子どもが小さいうちから、学資保険に加入するなどの方法で備えておきたいところです。
学資保険には、子どもの入学や進学にあわせて祝金・満期保険金を受け取れるタイプと、18歳から22歳までなど一定期間に毎年祝金が給付されるタイプがあり、原則として親が契約者・子どもを被保険者として契約します。
一般的に、子どもが死亡した場合は支払った保険料相当額程度の死亡給付金が給付されます。
学資保険は必要?
学資保険への加入が本当に必要かどうか、お悩みの方も多いと思います。学資保険は、計画的に教育資金を準備することが苦手な方向けの金融商品です。預金口座等から毎月保険料が引き落とされ、学資保険の一部として積み立てられることで、計画的に教育資金を準備することができます。
学資保険に加入するには、加入時期や保険期間を考慮して、適切なプランを選ぶようにしましょう。家計に余裕があり教育資金を十分に賄うことができる場合や、別の資産運用で教育資金を準備する場合は、学資保険に限定して検討する必要はありません。
学資用以外の保険商品で学資を準備するケースもあります。近年の金利情勢から外貨建ての商品などで代替する場合は為替変動による差損を考慮し、余裕資金の範囲内での対応を検討しましょう。
また、家計が苦しく保険料の捻出が難しい家庭にもおすすめできません。家計に余裕が出てきたタイミングで、あらためて検討するようにしましょう。
少子化対策として奨学金が拡充される傾向にあります。早いうちから奨学金制度について確認しておくことや学資は準備せずに奨学金で賄うと割り切ることも選択肢の1つです。
学資保険のメリット

学資保険には次のメリットがあります。
・学費以外にも使える
・契約者(親など)の死亡で保険料の払い込みは免除・保障は継続される
・保険料は一定の額まで所得控除の対象となる
それぞれのメリットを、次の項で詳しくみていきましょう。
学費以外にも使える
学資保険で受け取る給付金は、入学料や授業料以外の目的に使っても問題ありません。
寮やアパートの契約金や入居費用・仕送りをはじめ、使途は自由です。
契約者死亡で保険料払い込み免除になる特約を付加できる場合がある
学資保険では万が一、契約者が死亡した場合に、以降の保険料の払い込みが免除となる特約を付加できる商品があります。
この場合も保障は継続し、保険金は契約どおり受け取ることができます。
保険商品によっては、契約者の死亡後は所定の育英年金が給付されるタイプもあります。
保険料は一定の額まで所得控除の対象となる
学資保険の保険料は一般生命保険料として所得控除の対象となり、一定の限度額までは税制の優遇を受けられるメリットがあります。
年末調整の際は、保険会社から送られてくる控除証明書を含む必要書類を忘れずに勤務先に提出するようにしましょう。
学資保険の注意点
学資保険に加入するにあたっては、次の注意点もあります。
・契約時に年齢制限がある
・元本割れの可能性がある
・受取時に課税される
それぞれ詳しくみていきましょう。
契約時に年齢制限がある
学資保険では、ほとんどの場合、契約者(親など)と子どもの年齢に条件が設けられています。
保険会社によっても異なりますが、子どもは0歳から契約できることが多く、妊娠中から契約できる保険商品もあります。
上限は6歳や7歳が一般的ですが、12~15歳程度の場合もあります。
契約者の年齢制限も同じく保険会社により異なりますが、下限が16~18歳程度、上限は70~75歳まで取り扱っている場合があります。
元本割れの可能性がある
学資保険で給付される祝金や満期保険金の受取額は、支払った保険料の合計を下回る可能性もあります。
保険料の支払総額がいくらになり、将来どれくらいの保険金を受け取ることができるのか、シミュレーションを必ず行うようにしましょう。
なお、元本割れは中途解約によっても発生する可能性があるため注意しましょう。
受取時に課税される
契約者が一時金として保険金を受け取るときには、一時所得として課税されます。課税されるのは、支払済の保険料総額より保険金が50万円以上多い場合で、50万円を超えた部分の2分の1が課税対象となります。
また、一時金ではなく年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されます。
学資保険を選ぶときのポイント
ここからは、学資保険を選ぶときのポイントについて解説します。
具体的には、次の3点に注意して加入を検討しましょう。
・返戻率で選ぶ
・受取時期を決める
・保険料の払込期間・払込方法を決める
次項で詳細を解説します。
返戻率で選ぶ
支払った保険料に対して、どの程度のリターンを得られるか知っておくことが重要です。
保険料の総額に対する将来の受取金額の割合を返戻率といいます。この返戻率が100%を下回る場合は、元本割れということになります。
受取時期を決める
学資保険の保険期間は、18歳・22歳など一定の年齢で満期となります。満期の設定は商品内容により異なります。
一般的に、家計に特に影響があるのは大学の学費です。
したがって大学の進学時期に満期を設定するのがおすすめですが、子どもがどのような進学コースを辿るのかにもよっても違ってくるため、将来のプランにあわせて受取時期を選ぶようにしましょう。
保険料の払込期間・払込方法を決める
通常は保険料の払込期間と保険期間は同一ですが、払込期間を保険期間より短く設定すると、保険料の支払総額を減らすことができます。
一定期間分をまとめて支払うことで保険料の割引を受けられる「前納」を取り扱っている保険会社もあります。前納を利用でき、資金に余裕がある場合は検討するとよいでしょう。
教育資金に関するお悩みにはauマネープラン相談がおすすめ
教育資金の目安や学資保険のメリット・注意点はおわかりいただけたでしょうか。
子どもの学費については、一時的にまとまった額が必要になる場面が多いため、計画的に準備しておけば安心できます。進路によっても変わるので、子どもと日ごろから話し合っておくことも大事です。
とはいえ、どれくらいの額をいつぐらいまでに、どのような手段で準備するかを考えるのは大変でしょう。
auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談では、教育資金についてのお悩みをファイナンシャルプランナーに無料で相談することができます。
ファイナンシャルプランナーはお金のプロです。お客さまの家計のお悩み内容をていねいにヒアリングし、豊富な知識で的確なアドバイスを提供します。
教育資金や学資保険だけでなく、生命保険の見直し、住宅ローンや老後資金といった家計全般のお悩みを、ぜひお聞かせください。auマネープラン相談は、お客さまのお悩み解決に向けて、全力でサポートします。
ご希望のお客さまには、将来のお金の流れをまとめた、お客さまだけの「キャッシュフロー表」を作成いたします。費用は一切かかりません。auマネープラン相談では、何回でも何時間でも相談できます。
プロの意見を参考に、お金に関する疑問や不安を解消してみてはいかがでしょうか。
どんなことが相談できる?
auフィナンシャルパートナーに寄せられているマネープラン相談は、例えば以下のようなものです。
-
- 家計管理
- 貯蓄が増えないのは家計管理が問題?
- 今の家計で将来の資金は大丈夫?
-
- 老後資金
- 老後はいくらあれば安心?
- 効率的な老後資金の貯め方を知りたい
-
- リスク管理
- 保険ってよくわからない、そもそも必要?
- 私に合った保険か調べて欲しい
-
- 住宅資金
- 住宅ローン返済計画など、最適な選択肢を知りたい
- 購入すべきベストなタイミングはいつ?
-
- 教育資金
- 希望の進路に進ませるにはいくら必要?
- 効率的な資金準備の方法を知りたい
-
- 資産形成
- 老後資産を形成したい
- 早期退職のため資産形成したい
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが一人ひとりに合わせたキャッシュフロー表を作成し、お金に関するお悩み解決をサポートいたします。
auフィナンシャルパートナーなら
安心の品質!
-
お客さま満足度93.9%
私たちのサービスを実際に受けたお客さまの満足度は93.9%の評価を頂いています。
身近な節約から資産形成まで、お金の悩みは人それぞれ。さらにライフステージによって悩みも変化します。
お金のプロの視点から一人一人が安心し、豊かに過ごすために何度でも無料でアドバイスいたします。 -
累計相談件数15万件
当社は開業から5年で累計相談件数が15万件以上のサービスを提供してきました。
あなたが初めてではありません。
お金のプロとしての知見、そして15万件以上のご相談実績から安心してお金の悩みをご相談いただけると思います。 -
全国対応
お客さまがご都合の良い場所まで、私たちがお伺いします。
お金の相談をするために時間をかけて移動したり、慣れない場所で相談する必要はありません。
安心できる場所で、落ち着いて、お金に関するお悩みをお話いただけます。
気兼ねなくご要望をお聞かせください。
auフィナンシャルパートナーへの
ご相談の流れ
-
Step.1 相談予約
「予約ボタン」より必要事項とお電話希望時間帯、相談内容をお申込ください。
-
Step.2 予約のご確認
ご相談の日時、場所、相談内容などをオペレーターがお電話で確認させていただき、予約は完了となります。
-
Step.3 ご相談
お客さまのお悩みを解決するため、お金のプロに何度でも無料でご相談いただけます。
学資保険は早期から計画的に準備を
教育資金への備えは、少しでも早いうちから計画的にスタートさせましょう。学資保険ならお金を貯めることが苦手な方でも着実に資金を準備することができます。
保険選びや教育資金についてプロのアドバイスがほしい方は、auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談を活用してみましょう。
auマネープラン相談では、ファイナンシャルプランナーから無料でアドバイスを受けることができるので、お気軽にお申し込みください。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金