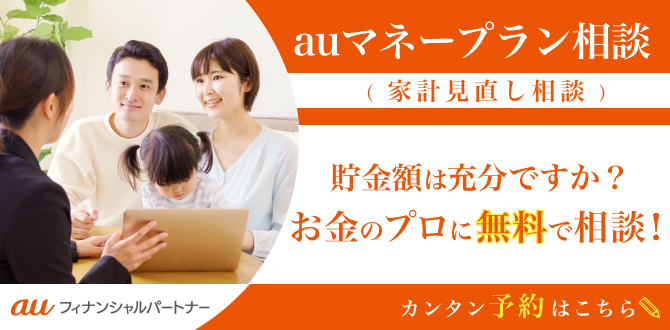住民税非課税世帯とは?対象となる条件や給付金をわかりやすく解説!

住民税は、身近な税金のひとつです。福祉や消防、教育などの行政サービスにかかる費用は、私たちが納めた住民税によってまかなわれています。
原則、自分が住んでいる市区町村(都道府県)に住民税を納める義務がありますが、一定の条件を満たす場合は、住民税の支払いを免除されます。住民税が課税されない世帯を、「住民税非課税世帯」といいます。
住民税非課税世帯の対象となるのは、どのような世帯なのでしょうか。今回は、住民税非課税世帯となる条件や、非課税となった場合どのような免除・減免を受けられるのかを解説します。また、住民税非課税世帯が対象となる給付金を紹介します。
住民税とは?
住民税は地方税のひとつであり、道府県民税(都民税)と市町村民税(区民税)を合計したものです。その年の1月1日時点で市区町村(都道府県)に住所がある人に課せられます。
徴収された住民税は、公共施設や学校教育などの行政サービスの活動費に充てられます。納税義務者は、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、所得にかかわらず定額を負担する「均等割」をあわせた額を納めます。
徴収方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類です。一般的に、会社員などは会社の給与から天引きされる「特別徴収」で差し引かれています。普通徴収は、市区町村から送達された納税通知書にしたがって納税する方法です。
一定の事由に該当し、課税対象から外されることを「非課税制度」といいます。低所得者層の負担を考慮した制度であり、扶養する家族の有無や所得などによって適用されるか決まります。
住民税非課税世帯の要件
非課税世帯の対象になるのは、所得額や扶養家族の有無などの条件を満たす場合です。
ここでは、住民税すべてが非課税になるケースと、住民税のうち「所得割」のみ非課税になるケースに分けて解説します。
住民税の所得割・均等割どちらも非課税となる条件
住民税のすべてが非課税となるのは、下記の条件(1)〜(3)のいずれかを満たす世帯です(※)。
(1)生活保護を受けている人
(2)障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4千円未満)の人
(3)前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人
「(3)前年中の合計所得金額」は、東京23区の場合、下記のように算出します。
・(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合)35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養家族の人数)+31万円以下
・(同一生計配偶者および扶養親族がいない場合)45万円以下
条件となる合計所得金額に関しては、住んでいる市区町村に確認しましょう。
(※)出典:総務省「個人住民税」
住民税の所得割が非課税となる条件
住民税で納めるのは、所得によって決まる「所得割」と平等に課せられる「均等割」の合計額です。そのうち、「所得割」が非課税となるのは、前年中の合計所得金額が一定額以下の世帯です。
下記のいずれかに該当する場合、住民税の所得割額は免除されます(※)。
・(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合)35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養家族の人数)+42万円以下
・(同一生計配偶者および扶養親族がいない場合)45万円以下
(※)出典:総務省「個人住民税」
住民税非課税世帯は年金や保険料が安くなる
住民税非課税世帯となった場合、公的保障の保険料はどの程度免除されるのでしょうか。ここでは、国民年金と国民健康保険の保険料の免除制度や減額措置を説明します。
国民年金保険料
国民年金には保険料の法定免除制度があり、「生活保護の生活扶助を受けている」人は対象となります。生活保護を受けはじめた日を含む月の前月の保険料から免除されます。
免除制度を適用するには、国民年金担当窓口へ「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出しなければなりません。生活保護を受けている住民税非課税世帯は、忘れずに手続きを行いましょう。
また、下表のように「本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下」の場合にも、保険料免除制度を受けられます。
| 保険料免除制度 | 承認される所得の基準 (2021年度以降) |
免除された期間の年金額 (2009年4月分以降) |
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 保険料を全額納付した場合の年金額の1/2 |
| 3/4免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の5/8 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の6/8 |
| 1/4免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の7/8 |
(※)出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を元に筆者作成
保険料を全額納めた場合と比べると受け取れる年金額は少なくなりますが、免除制度の手続きを行わずに未納となった場合、税金分の年金も受け取れません。所得が少ないなど、経済的に保険料を納めるのが難しいのであれば、免除制度を申請しましょう。
保険料の免除だけでなく、納付猶予制度もあります。本人・配偶者の前年所得が下記の計算式で算出した金額の範囲内であれば制度の対象です(※)。
・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
納付猶予の期間は、老齢基礎年金などを受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。しかし、追納しない場合、受給できる年金額が増えない点には注意しましょう。
免除・納付猶予制度を受けるためには、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」などの書類を市区役所または町村役場に提出する必要があります。
国民健康保険料
今回は東京都北区を例に挙げて、国民健康保険料の減免制度を解説します。
国民健康保険料は、算定基礎額をもとに計算した「所得割額」と「均等割額」をあわせて算出します。算定基礎額とは、前年の総所得金額(退職所得金額を除く)から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
東京都北区では下表のとおり、それぞれ医療分・支援金分・介護分の所得割額と均等割額を合計して年間保険料を決めます。
| 国民健康保険料 | 基礎賦課額(医療分) | 後期高齢者支援金等賦課額(支援金分) | 介護納付金賦課額(介護分) |
| 所得割額 | 加入者全員の算定基礎額×7.16% | 加入者全員の算定基礎額×2.28% | 加入者全員の算定基礎額×2.39% |
| 均等割額 | 42,100円×加入者数 | 13,200円×加入者数 | 16,600円×加入者数 |
(※)東京都北区「国民健康保険料の計算方法」を元に筆者作成
また、前年の総所得金額が、下記の計算式で算出した金額以下の世帯は、国民健康保険料の均等割額が減額されます。
| 減額割合 | 世帯の総所得金額(2021年) |
| 70% | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
| 50% | 43万円+28.5万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
| 20% | 43万円+52万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
(※)東京都北区「保険料の軽減(国民健康保険)」を元に筆者作成
住民税の申告を済ませてあれば、手続きは不要です。国民健康保険料の軽減・減免制度は各自治体で実施されているため、自分の住んでいる市区町村へ確認しましょう。
住民税非課税世帯の給付金

住民税非課税世帯が対象となる給付金はあるのでしょうか。ここで、住民税が課税されない世帯へ向けた給付金を2つ紹介します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)や住民税均等割非課税の子育て世帯に支給されます。
支給額は児童1人あたり一律5万円で、市区町村によって支給時期が異なります。
受給条件や申請方法など詳細の情報については、自治体ごとに異なります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
電力・ガス・食料品等価格高騰に伴う支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、各自治体は低所得世帯に対して1世帯あたり3万円を給付しています。
受付開始時期や、対象者、申請方法、支給予定日などの詳細については、自治体ごとに異なります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
どんなことが相談できる?
auフィナンシャルパートナーに寄せられているマネープラン相談は、例えば以下のようなものです。
-
- 家計管理
- 貯蓄が増えないのは家計管理が問題?
- 今の家計で将来の資金は大丈夫?
-
- 老後資金
- 老後はいくらあれば安心?
- 効率的な老後資金の貯め方を知りたい
-
- リスク管理
- 保険ってよくわからない、そもそも必要?
- 私に合った保険か調べて欲しい
-
- 住宅資金
- 住宅ローン返済計画など、最適な選択肢を知りたい
- 購入すべきベストなタイミングはいつ?
-
- 教育資金
- 希望の進路に進ませるにはいくら必要?
- 効率的な資金準備の方法を知りたい
-
- 資産形成
- 老後資産を形成したい
- 早期退職のため資産形成したい
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが一人ひとりに合わせたキャッシュフロー表を作成し、お金に関するお悩み解決をサポートいたします。
auフィナンシャルパートナーなら
安心の品質!
-
お客さま満足度93.9%
私たちのサービスを実際に受けたお客さまの満足度は93.9%の評価を頂いています。
身近な節約から資産形成まで、お金の悩みは人それぞれ。さらにライフステージによって悩みも変化します。
お金のプロの視点から一人一人が安心し、豊かに過ごすために何度でも無料でアドバイスいたします。 -
累計相談件数15万件
当社は開業から5年で累計相談件数が15万件以上のサービスを提供してきました。
あなたが初めてではありません。
お金のプロとしての知見、そして15万件以上のご相談実績から安心してお金の悩みをご相談いただけると思います。 -
全国対応
お客さまがご都合の良い場所まで、私たちがお伺いします。
お金の相談をするために時間をかけて移動したり、慣れない場所で相談する必要はありません。
安心できる場所で、落ち着いて、お金に関するお悩みをお話いただけます。
気兼ねなくご要望をお聞かせください。
auフィナンシャルパートナーへの
ご相談の流れ
-
Step.1 相談予約
「予約ボタン」より必要事項とお電話希望時間帯、相談内容をお申込ください。
-
Step.2 予約のご確認
ご相談の日時、場所、相談内容などをオペレーターがお電話で確認させていただき、予約は完了となります。
-
Step.3 ご相談
お客さまのお悩みを解決するため、お金のプロに何度でも無料でご相談いただけます。
まとめ
生活保護を受けていたり、前年の所得金額が少なかったり一定の条件を満たせば、住民税非課税世帯の対象となります。
住民税が非課税となる場合は、同様に国民年金や国民健康保険料の免除・減免制度が適用となる可能性があるため、忘れずに確認しましょう。
非課税制度や保険料の免除などを受けるために、自分で申請手続きを行うケースがあります。困っている時はひとりで悩まず、お住まいの自治体に相談することをおすすめします。
カテゴリ
ピックアップ | 家計見直し・教育資金
ピックアップ | 住宅ローン
ピックアップ | 保険見直し
ピックアップ | 資産形成・老後資金
カテゴリ別人気ランキング
- 家計見直し・教育資金
- 住宅ローン
- 保険見直し
- 資産形成・老後資金